デジタルツールのリスクと対策
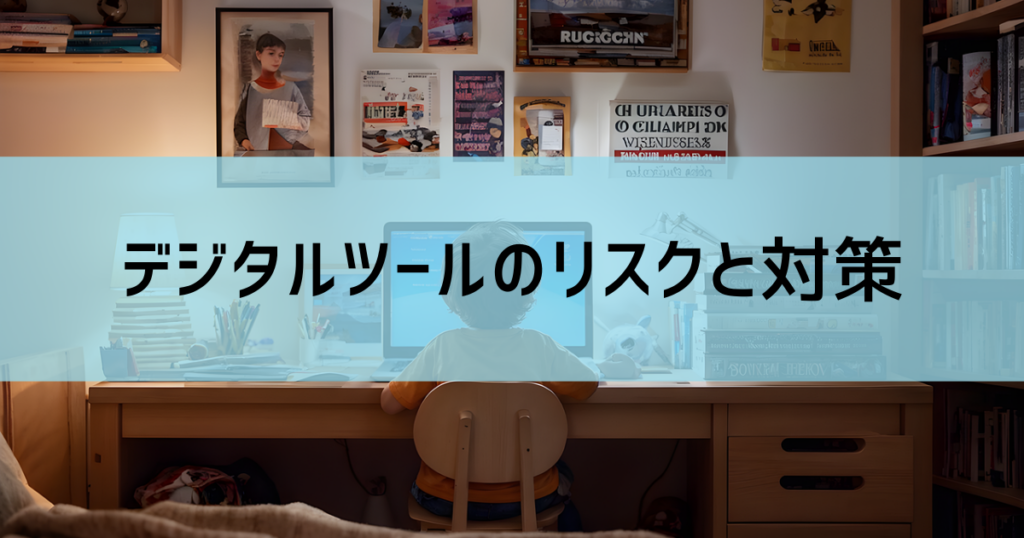
同施設にあるフリースクールで、日々子どもたちと一緒に学び、向き合う中で、ネットの使い方は多く課題として上がることがあります。その中で、私たちの考えを共有させていただきます。
現代社会でSNSやAIツールの利用を完全に絶って生活することは、現実的ではない理由
- 情報格差が生まれる:AIツールやSNSは使いこなすことができれば、細かい疑問を即時解決して学ぶ時間を短縮。浮いた時間をさらに自分の興味を深掘りができます。この+αが勉強の楽しいところです。
- 新しい機会や興味に触れる機会を失う:子どもたちはインターネットを通じて、好きなことを学び深めたり、創作活動や趣味を見つけたりできます。
- 学習や自己表現の機会が減る:興味を深掘りしたり、自分の意見を発信する練習が不足してしまい、好奇心や自己表現の幅が制限されるかもしれません。
- 社会とのつながりや最新情報へのアクセス:SNSなどを通じて、子どもたちは社会の動きや多様な考え方を知り、他者とのつながりを持てます。友人関係や社会性を築くうえで、一定のオンライン環境は必要になってきています。
- デジタルリテラシーを養う:将来インターネットを使うときに戸惑う可能性があります。情報の信憑性を見分ける力は、今後さらに重要になるスキルです。
- 将来のスキルやキャリアに影響が出る可能性:デジタルスキルは、ほとんどの職業で重要視されている能力です。特に情報収集やデジタル表現のスキルが必要な仕事では、早くから経験している人の方が優位に立つことが多いです。
親子でゲームやネットの利用について考えることが大切
ゲームやインターネットは、戦略的思考や創造性を育てる学びのツールとして活用できるだけでなく、家族のコミュニケーションを深める手段にもなります。大切なのは『使わせるか・禁止するか』ではなく、『どのようにやるか』です。また、適切なルールの下で利用することで、自己管理能力を養い、将来の学びや仕事に役立つスキルを身につけることができます。
家庭で取り組むポイント
時間だけではなく、場所も決めることをオススメしています。ネットやゲームをする場所を決めることで、親の目が届きやすく、安全性が確保され、使用時間の管理もしやすくなります。また、共有スペースでの利用はルールの一貫性を保ち、遊びと勉強のメリハリをつけることで集中力の向上にもつながります。
- リビングでやる
- スマホゲームは親のいるところでやる
など、家庭の状況に合わせてルールを決めましょう。
保護者の方が興味を持ってあげることも有効です。「どのキャラクターが好きなの?」『それはどうやって遊ぶの?」など、いろいろ質問してあげてください。オープンに話せる環境を作れれば隠し事もしなくなり、親の不安も少し軽減されるはずです。親が自分の好きなものに興味を持って一緒に話しをしてくれるというのは、子どもにとって最高の時間になるはずです。また、本や教科書などのアナログな情報源からも学ぶ時間を持つことで、バランス良く成長できるようサポートしましょう。
約束が守られなかった時のペナルティについて
ペナルティは子ども主体で決めるのが望ましいです。
- 翌日はゲームをしないようにする
- 一週間ゲーム禁止にする
など、子どもでもきちんとペナルティは考えられるはず。
「たとえば・・・.』と保護者の方が例を挙げて決めさせるのも良いでしょう。
約束したペナルティは必ず実行すること。そのためには、必ず実現可能であるペナルティを親子で一緒に話し合って作ることが大切です。
- 宿題が終われば時間制限はなし
- 週末は親子で思い切りゲームを楽しむ
- 30分やるたびに休憩する
- 平日はゲームなしで、土日は4時間OK
など、ルールはさまざま。子どもの性格や年齢だけでなく、兄弟がいるか、どんなジャンルのゲームをやっているか、親もゲームが好きかなどで、状況は異なります。世間一般のルールに合わせるのではなく、それぞれの家庭のオリジナルルールを決めるようにしましょう。その方が、ルールを守れる確率が上がり、親子ともにストレスなく過ごせるようになります。
以下は懸念される内容と対策です。
1. 情報過多で集中力や記憶力が低下するのでは?
- 懸念内容:インターネットで簡単に情報が手に入ることで、記憶力や集中力が低下する可能性があります。
- 対策:デジタルツールを使う前に「まずは自分で考える」「要点を自分の言葉でまとめる」といった習慣づけをサポートします。また、利用時間を制限することで、メリハリをつけて効率的に勉強することができます。
2. 思考力の低下についての心配
- 考えるプロセスのサポートとして活用する
ChatGPTや検索エンジンは、答えそのものを探すためだけではなく、考える過程をサポートする道具として活用できます。例えば「どういうアプローチで解けるか」や「調べるときのヒント」を得るための手段として使うことで、自分の考えを深めたり、アイデアを広げたりする力が養われます。 - アウトプット前提で知識を整理する
ただ思考停止で答えを聞くのではなく、誰かに発表することを前提に検索し、見つけた情報を自分で整理する習慣がつくと、思考力が身につきます。 - 好奇心を育てるツールとして使う
興味があるトピックを調べる際にも、「どうして?」や「なぜ?」を深掘りできる質問をChatGPTに投げかけると、次の疑問が生まれやすくなります。自分の疑問を起点にして知識を深めることが、好奇心と探求心を育てることにつながります。
3. プライバシーやセキュリティの不安
- 懸念内容:個人情報がネット上に漏洩する、または詐欺に遭遇する危険性があります。
- 対策:子どもがアカウントを作成する際は保護者が見守り、プライバシー設定やパスワードの管理を行います。インターネット上では「知らない人とやり取りしない」「怪しいメッセージやリンクにはアクセスしない」「人の名前、住所、電話番号、学校名など、個人が特定される情報は絶対に伝えない」などのルールを守るよう指導します。
4. 発達やコミュニケーション能力への影響
- 懸念内容:インターネットを通じたやり取りが中心になると、社会性や表現力が育ちにくくなる恐れがあります。
- 対策:インターネットで得た知識を、家庭内でシェアしてもらう機会を設けると、学んだ内容を家族と話す練習にもなります。
5. 誤った情報や偏った情報の影響
- 懸念内容:ネット上には正しくない情報や偏った見解が存在し、子どもが誤った考えを持つ可能性があります。
- 対策:
- 本や信頼性の高いウェブサイト(たとえば公共機関や教育機関の公式サイトなど)で同じ情報を調べてみる。
- ChatGPTに「この情報の出典は何?」や「具体的な根拠を教えて」と尋ねる。
- 保護者も一緒に情報の確認を行い、話し合いながら正確な知識を共有することが望ましいです。
- 違う視点からの情報を比較し、内容の一致や相違点を探る
6. 悪影響な情報への対応
- 悪影響なコンテンツの制限:SNSやインターネットには暴力的な内容や、不適切な表現を含むものもあります。保護者向けのフィルタリング機能を活用し、年齢に合った安全なコンテンツだけが表示されるように設定しましょう。
- オープンな話し合い:万が一、不適切な情報を見てしまった場合には、「なぜその情報が悪影響なのか」「どう対処するべきか」を話し合い、感じたことや心配な点について気軽に話せる環境を作ることが重要です。
上記のような配慮をしながら、教育プログラムを設計しています。その他に心配な点やご不明な点がありましたら、以下の公式LINEからお問い合わせ、もしくは体験レッスンにお越しください。

